インターネット上で炎上が起こると、当事者が公開する「謝罪動画」には大きな注目が集まります。しかし、中には視聴者の予想を裏切る形で真っ暗な映像だけが流れるケースもあり、その意図について議論が起こります。この記事では、そのような異例の謝罪動画がなぜ公開されるのか、考えられる理由や背景を解説します。
謝罪動画に求められるもの
一般的に謝罪動画は、本人が顔を出し、誠意を示すことが重要だと考えられています。表情や声のトーンなど、非言語的な要素が信頼回復に大きな役割を果たすからです。そのため、真っ暗な動画は視聴者に誠意を欠いているように映りやすく、批判を招きやすいといえます。
真っ暗な動画を出す心理的背景
真っ暗な動画を謝罪の場に使う背景には、いくつかの心理的要因が考えられます。
- 強い心理的ストレス:顔を出すことへの抵抗や恐怖心。
- 意図的な拒絶:謝罪の形式を取りながらも、批判者に迎合しない姿勢を示す。
- 演出としての逆効果:無言や暗闇を「演出」として使うが、受け手には誠意不足と映る。
これらの要素が複合的に絡み合い、結果的に「火に油を注ぐ」形になってしまう場合があります。
過去の事例から学べること
過去の炎上事例を振り返ると、真摯に対応したケースは一定の理解を得やすい一方で、ふざけた態度や不誠実と取られる対応は批判を長引かせる傾向があります。特にSNS時代においては、わずかな対応の差が信頼回復かさらなる炎上かを分けてしまいます。
真っ暗な動画のように「意図が見えにくい謝罪」は、誤解を招きやすく、ほとんどの場合マイナスの効果しかありません。
本人に得はあるのか?
結論から言えば、真っ暗な動画を出すことで得られるメリットはほとんどありません。短期的には話題性が高まり再生数が伸びる可能性はありますが、中長期的には信頼低下やイメージ悪化につながります。ブランドや個人としての立場を考えると、リスクのほうが圧倒的に大きいのです。
まとめ
謝罪動画が真っ暗であることは、視聴者に誠意を伝えるどころか、逆に不信感や怒りを増幅させる結果になりやすいといえます。心理的な葛藤や演出意図があったとしても、炎上後の対応では「誠実さ」「透明性」「具体性」が最も重視されるため、顔を出して自分の言葉で説明することが、結局は最も有効な収束方法となります。
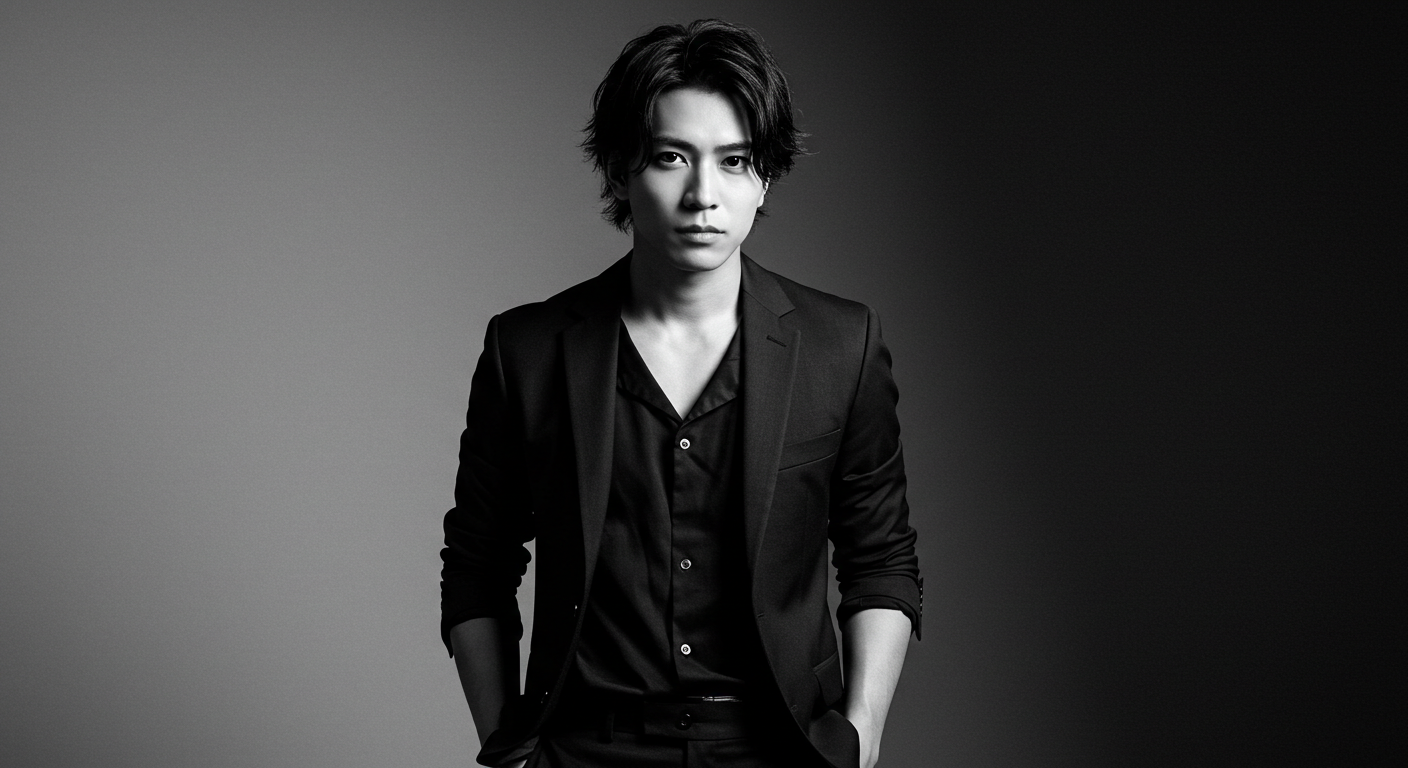


コメント